※ 「石原説」によって眼の色覚構造が解ると(本文 Page2 Page3-2 参照)今までの色覚理論も収拾し理解出来る様になります。
| 2013年3月23日 (土) |
色 と は、人 の 感 覚 で あ る |
現在、多くの方々は色を感覚としてのみ理解しているのではなく、質的量的、物の様な概念で(客観的対象物の様に)色を理解していると私は考えています。
それは、色と言う概念が工業規格や色彩学では数値や記号によって定量化し規格とされ、質的量的、感覚で利用出来るようになっている事、同じ光源での色比較では、お互いが殆ど同様な質的感覚で色物の区分がされ、又、色を質、量の様に表す言葉に「色の付き具合、色を重ねる」等と言っている事からです。
色は主観的な(感覚的)ものでありながら客観的な(目の前の対象物の様な)ものとして扱われている事が普段の生活の中では殆どではないでしょうか?
例えば、塗装、染物、印刷屋さんは(主観的)色の見え方、濃淡を(客観的対象物の)顔料の種類、多少と関連づけ、電気屋さんは(主観的)色光の見え方、明暗を(客観的)発光物の種類、電気の強弱と関連させ理解しているのではないでしょうか?
「リンゴは■赤いから■赤く見える」一見正しい理解に思えますが、リンゴが(主観的に)■赤く見えるのは(客観的)対象物であるリンゴの表面が■赤として感ずる光の波長を反射させる性質の為で、それを人が■赤と認識するのは「(主観)感覚を司る眼の感覚神経による」と理解するのが正しい考え方ではないでしょうか?(又、光は現代物理学では空間を伝わる特定波長帯の電磁波と解っていて、その波長の違いを人は色として感ずるのであり、光に色と言う性質が有る訳ではない。)
花を見て「美しい」と感ずるのは(主観的)人の心であり、花は人に「美しい」と言う感性を司らせる何か(客観性)を持っているとは言えても、花自体には「美しい」と言う物は無く、「花が美しい」と言う感覚(価値)は花と人との相対関係で生ずるものである事が解ります。
「リンゴが■赤い」と言うのも、人に■赤と認識させる何か(客観性)をリンゴが持っているとは言えても、リンゴその物が「■赤い」訳では無いと理解するべきで、人が■赤と感ずる光の波長を反射させたリンゴと人との相対関係で生ずる人の感覚であると理解すべきと考えます。
(リンゴに当てる光を■赤と感ずる波長以外の単一波長光を当てたとしたら当然、別な感覚(色)として認識される。)
色を扱う多くの方々も正確には正しい理解ではなくても、便宜的に質的量的、目の前に有る物(客観的対象物)と同様な扱いをする事で色を理解しているのではないでしょうか?
さて、色覚説には大まかに分けて、三原色説と反対色説と有ります。「三原色説」は色を質的量的、客観的概念に近い感覚で説明された説、「反対色説」は経験的、感覚的、主観的概念を全面に説明された説と私は理解しています。(「石原説」は後者からの派生)また、「三原色説」は光学等の分野では広く応用され普及していますが、「反対色説」は現実的な応用範囲が殆ど無い為、色覚説と言う場合、「三原色説」の事を指すのはその為と思われます。
ところで、色覚の専門家や眼科の先生が色覚異常について説明したものは、なぜ「三原色説」での説明が殆どなのでしょうか?
多くの方が(主観的)色を(客観的)質的量的、物と関連付け理解している様に、先生方の色覚異常に対する理解も(主観的)色の見え方を(客観的概念に近い)「三原色説」を元に、有るとする三種の網膜円錐体と関連させ、色の見え方の症状を円錐体(客観的な物)の有無、機能不全とする事で理解されているからではないでしょうか?
「三原色説」を元にした理論では「石原式色覚検査表」を論理的に説明する事が難しくても、それをスクリーニングのみの使用とする事で、一般方々の色に対する理解と通ずるものとして、現代医学は色覚異常を説明しようとしているのでしょうか?しかし「石原説(表)」「反対色説」「補色法則」等で感覚(主観)としての色覚理論を理解すると質的量的、三原色的概念だけで説明出来る事柄では無いと分かり「色をその様に表現するのは、あくまで便宜的な事柄として利用する為」との見解を理解できる様になります。
本質を扱う、医、科学の分野は、「三原色、反対色説」の違い、色覚異常の症状の違いも眼の構造、発育との関連によって収拾し説明する「石原説」であるべきと思えます。
仏教の経典「般若心経(はんにゃしんぎょう)」の中に「色即是空(しきそくぜくう)」というお経の句が有ります。その中の「色(しき)」は現在日本で使われている「色」の意味とは違い「物、形」としての概念も含むそうですが、「見えている物(色)すなわちそれは空である(感覚的なものに過ぎない)」と考えると、このお経の持つ意味の一端を理解出来る様になります。
色とは、物(の性質)でも光(の性質)でもない、目で感じて有ると思う事の出来る人の感覚なのです。 |
|
 page top page top
| 2013年1月26日 (土) |
真 偽 を 見 極 め る |
世の中は、(戦争などの)人の活動を除けば、宇宙の秩序によって動き、全ての存在は、それ以前からある原則、理法によって、誰が教えるでなく、赤ん坊がこの世に生まれれば、目を開けて呼吸をするように、無理矢理でなく「おのずとそのようになる」ようになっています。それこそが「世の中の秘密を解く鍵」と私は考えます。
「 物事の真偽 」本来それは、世間の評判、慣習、権威、あるいは、個人的な損得などによるのではなく、宇宙の原則、秩序との対話によって見いだされるべきものではないでしょうか?
石原忍先生の診療訓にも「自然に反せず人力を尽し」とあるように「自然界の法則、秩序」それと「人が努力する心」を重んじられていた事が分かります。
無理矢理な、すりかえられた?論理では、人を騙す事は出来ても、人の色覚でさえ万人が納得出来る説明をする事は、実際、不可能である事を多くの方が理解され、この問題に対して真摯な対応がされます事を心より願います。
※そもそも、色彩理論、色覚理論とは物理的な科学理論などではなく、聴覚、味覚等と同様、心理学の分野に属する感覚理論である事を、殆どの人々は学校の授業等で物理的科学理論と混在された理論として教わる為「色を物体の性質、或いは、光の性質で有る」との間違えた認識のまま、三原色説等の色覚理論を理解されている事が問題の根底にある様に思えます。(それは戦後GHQによって行われた歴史文化の改竄、隠蔽、唯物的科学理論への偏重と同様な事が色覚説や医学理論にも行われた?からなのでしょうか?)(2025.02.27 追記)
※「石原 忍先生は戦前、戦中、戦後と活躍された尊敬すべき医学博士であった」と私は思っています。その先生が作られた石原式色覚検査表、その序文の(石原表の理論を消し去る目的?かの様な)改変が戦後、石原先生没後、それも「偽の色覚治療をする」とされた治療院が有った時期と同時期に行われた事に疑念を持っています。色覚問題当事者として「正しい事柄を正しいと表現できる」そんな日が一日も早く来る事を心より願っています。(2025.03.07 追記)
|
|
 page top page top
| 2025年2月16日 (火) |
現 実 に は 存 在 し な い 不 可 能 な 色 |
混色には、■赤っぽい■緑(或いは■緑っぽい■赤)、■青っぽい■黄(或いは■黄っぽい■青)は存在しない。
補色関係にある原色の■青(紺)と■黄、または■赤と■緑が、混ざりあった色が存在しない事をご存知でしょうか?(頭の中で、想像しようとしても、その色をイメージする事すら出来ない……)さて、それは何故なのでしょうか?
答えは、「色とは光の性質でも物体の性質でもなく、目の(神経)構造が色を決定させ、認識させているからです。」
| →色 | 覚 | の 成 長 過 | 程 | → |
| | (青) | — | (青) |
| (白) | < | | | (緑) |
| (黒) | | (黄) | < | |
| : | | : | | (赤) |
| : | | : | | : |
| 第1期 | | 第 2 期 | | 第3期 |
「石原説」でも説明している様に、人間の目は、最初 白と■黒が見える様に成長し、更に、その中の 白と■黒が見える様に成長し、更に、その中の 白が■青と■黄に分化する。実際■青と■黄を光で混ぜると 白が■青と■黄に分化する。実際■青と■黄を光で混ぜると 白になります。
又更に、その中の■黄が■赤と■緑に分化する様に成長する。実際、光で■赤と■緑を混ぜると■黄になる。
光で■青■赤■緑を混ぜた場合、 白になります。
又更に、その中の■黄が■赤と■緑に分化する様に成長する。実際、光で■赤と■緑を混ぜると■黄になる。
光で■青■赤■緑を混ぜた場合、 白になるのは、その様な目の構造的成長過程が有るからです。
従って、( 白になるのは、その様な目の構造的成長過程が有るからです。
従って、( 白と■黒)■青と■黄、■赤と■緑は、同一感覚神経のプラス-マイナスの様なものと考えられ、原色の補色関係にある■青と■黄、■赤と■緑を混ぜ合わせた色が出来ない(存在しない)のは、目の構造によるものです。
また、■黄緑や、■橙なども、■黄の光を使わずとも、■赤と■緑の光だけで、作る(認識される)事が出来るのも、■黄の混色でありながら、片方の色が、目の構造と発光の加減によって■黄と認識されてしまう為に起こる(視神経を含む)目の中での現象である事が分かります。ゆえに、 白と■黒)■青と■黄、■赤と■緑は、同一感覚神経のプラス-マイナスの様なものと考えられ、原色の補色関係にある■青と■黄、■赤と■緑を混ぜ合わせた色が出来ない(存在しない)のは、目の構造によるものです。
また、■黄緑や、■橙なども、■黄の光を使わずとも、■赤と■緑の光だけで、作る(認識される)事が出来るのも、■黄の混色でありながら、片方の色が、目の構造と発光の加減によって■黄と認識されてしまう為に起こる(視神経を含む)目の中での現象である事が分かります。ゆえに、 明■暗と■青(紺)■赤■緑の三原色だけで全ての色を作る事が出来る様になります。
この様に理解すれば、色覚の段階説は必要無く、三原色説、反対色説も統合された理論として理解出来る様になります。 明■暗と■青(紺)■赤■緑の三原色だけで全ての色を作る事が出来る様になります。
この様に理解すれば、色覚の段階説は必要無く、三原色説、反対色説も統合された理論として理解出来る様になります。
詳しくは、3-2-3. 補色残像、二極性、四つの原色「石 原 説」で理解する色覚認識 へ。
外部Link YouTube動画 補色残像(補色関係にある■青■黄、■赤■緑、通常では混ざりあえない事を視覚を通し理解出来る。)
ひまわり写真による補色残像効果 YouTube ライラックチェイサー YouTube 現実には存在しない不可能な色 YouTube
|
|
 page top page top
| 2012年11月11日 (日) |
も う 一 つ あ る 三 原 色 |
「三原色」には、「光の三原色」と「色(材)の三原色」の他に、もう一つあります。それは、伝統的に用いてきた「■赤■青■黄の三原色」です。信号機も、歌にもあるように原色である♪●赤~●青~●黄色♪で作られています。昔は、この「三原色」で印刷が行われていた事も有った様です。現在でも絵画教室では、これを「三原色」と言っているのではないでしょうか?
小学校の図工の時間、先生が、この「三原色」の話をされ■緑の作り方を教えてもらった記憶をお持ちの方は結構多いと思います?そう「■青と■黄を混ぜると■緑が出来る!」という話です。
「それ何か、ヘンでは有りませんか?」「石原説」や「補色法則」から考えたら、光では無色、色材では無彩色(灰色)になるはずですよね?女房もその事に気がつき、「学校で、そのように教わった」と私に疑問をぶつけてきました。
さて、この件に関して、どのように考えたら良いのでしょうか?
ヒントとして、「色相環サークル(Google )で補色である対角線上の色を確認する」或いは「■黄や■青を凝視し補色残像で、その色の補色を体験的に見る」事で回答が得られるのではないでしょうか?
答えは、■黄の補色は青と言う事には間違い有りませんが、どちらかというと、紺に近い■青紫が■黄の補色としての青なのです。
青と言えば、青空の■青の事を一般的に思い描きます。しかし「■黄の補色の青は、■青紫のことを言っていた」という話です。
色相環サークルで青空の■青は、■黄の対角線上にはなく、■緑の方向に傾いた位置に有ります。「今まで理解していた、絵の具の■青は青そのものではなく■シアン(青緑)であった」と言えるのかもしれません?■青紫と■黄が補色として打ち消され無彩色となった時、残った■緑成分が目に入り、■緑に見えると理解すればいいのではないでしょうか?
でも、「■青の中に■緑成分が隠れていたとは?」 今でもまだ個人的には納得が出来ていません。
※ところで、絵の具の■青と■黄を混ぜる事で出来る■緑は何故、綺麗な■緑に成らないのでしょうか?
それは■青に含まれている■緑成分が、そもそも少ない事、■青成分中の■青紫と■黄を混ぜる事によって出来る無彩色(灰色)が純粋な■緑成分を濁してしまう程、量的に多い事が原因ではないでしょうか?「石原説」で考えると綺麗な■緑が■青と■黄の混色では出来ない理由も説明する事が出来る様になります。(2016.02.16追記)
|
|
 page top page top
| 2012年11月3日 (土) |
何 故、光 の 三 原 色 と 色 の 三 原 色 は 違 う の か? |
「色彩学」には、「光の三原色」と「色(材)の三原色」と有ります。
「光の三原色」は、■青■赤■緑の光で人が感知出来る、殆どの色を表せる事からそれを言い(テレビの三原色 参照)、紙等に印刷する時使う色の三原色」は、■青■赤■緑の補色である■黄■シアン(青緑)■マゼンダ(紫)を言い、それに■黒を加えることで過不足なく人が感知できる色彩を印刷などで表現できる様になります。
「石原説から考える原色とは、眼の構造に由来するもの」であり、無色から■青■黄、■黄から■赤■緑に分化されて出来た、■青■黄■赤■緑が原色となります。
その様に考えると、印刷等に用いる「色の三原色」中で■マゼンダは■赤と■青の混色、■シアンは■緑と■青の混色となります。紙への印刷は、色(材)を重ねる度に暗くなる性質の為(補色、反対色同士が色の明度を打ち消し合う為)(減法混色)、原色中で明度の高い■黄、■赤と■青の二つの色覚センサーを使い明度の高い■マゼンダ、■緑と■青のセンサーを使う■シアンが「色の三原色」と言われていると理解できます。
印刷では、■マゼンダと■黄を混ぜると■赤、■シアンと■黄を混ぜると■緑、■マゼンダと■シアンを混ぜると■青の「三原色」が現れます。■マゼンダ中の■青成分と■黄は補色関係の為、混ぜると無彩色(灰色)になり■赤のみが感知され、■シアン中の■青成分と■黄も同様に無彩色となり■緑のみ感知され、また、■マゼンダ中の■赤成分と、■シアン中の■緑成分が反対色関係の為、互いの色を相殺し無彩色となり■青のみ感知される為、■青■赤■緑の「三原色」も印刷で表示できるようになると「石原説」や「補色法則」から理解できます。
何故、「光の三原色」と「色の三原色」が違うのか?「石原説」からだと眼の構造を元に相互関係を理解できるようになります。
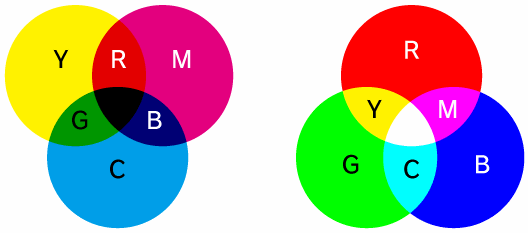 |
|
 page top page top
| 2012年11月01日 (木) |
改 め て、ご 挨 拶 |
| 「石原説ウェブサイト」を見てくださり、どうも有り難うございます。
「色覚」に関する話題を中心に、本文に載せるには、形にはならない日々の生活の中で思うこと、話題の事柄など、思いついたように日記ページに書いていきたいと思います。 (そろそろ、ネタ切れ?)
よろしくお願い致します。 「石 原 説 ウェブサイト」管理者(Cb.49) |
|
 page top page top
|
|